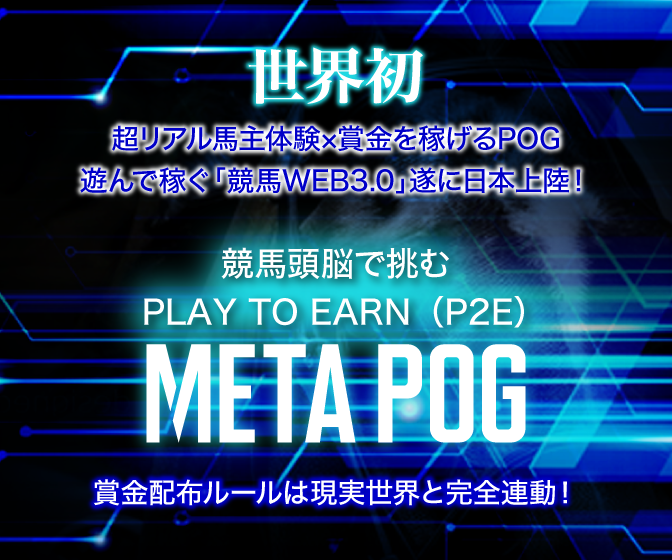今季の男子ゴルフツアーは5戦が終了し、初優勝が4人。フレッシュな面々の活躍が目立つが、ここから存在感を示して欲しいのが蟬川泰果。
2023年までにアマチュア優勝を含め通算4勝をあげた24歳の蟬川は、24年は未勝利に終わった。
そして今季は開幕前に怪我で出遅れた。蟬川の日本ツアー初戦は第3戦。ここまで2戦しか出場できていない。
ただ、その2戦とも優勝争いはできなかったものの、スイング調整の面で、これからの戦いに向けて手ごたえを感じているようだ。
◆恵まれた体格だけではない 河本力、幡地隆寛のスイングに見る飛ばしのポイント
■ケガで出遅れ
2022年にアマチュアとして日本オープンを含めツアー2勝をあげた蟬川。ルーキーイヤーとなった23年も2勝をあげ、賞金王を争った中島啓太、金谷拓実とともに“NSK”として、世界への飛躍を期待された。
しかし、24年は未勝利で、賞金ランキング19位。中島は欧州ツアーに、金谷は米ツアーに主戦場を移す中、蟬川だけが取り残された形となっている。
今年こそはと、スタートした今季だがいきなり不運に見舞われた。日本ツアー開幕前の米下部ツアー参戦中に、肋骨を疲労骨折。日本ツアー初戦は、今月1日から開催された中日クラウンズとなり、60位タイ。
追い風が吹かない蟬川だが、ここへきて表情は明るい。
日本プロでは最終的には13位タイだったが初日は2位スタート。その初日は14ホールでパーオンし、パーオン率が2位タイとショットが向上気配を漂わせた。
4ラウンドトータルで見ても、パーオン率10位タイで及第点のショット精度を見せた。
今季米ツアー初優勝をあげ、世界ランキング現時点29位のミンウー・リーのスイングを参考にしたことが功を奏したようだ。
■飛距離優先のスイング
昨季のドライビングディスタンス6位の蟬川は飛距離優先のスイングである。
バックスイングでクラブを深い位置まで持ってくる。トップの位置は、クラブヘッドが少し垂れ下がるオーバースイングで、シャフトが飛球線と平行ラインよりも右を向くシャフトクロス。
オーバースイングは、切り返しからインパクトまでのヘッドの助走距離が長くなるため、飛距離が出やすくなる。
シャフトクロスも、クラブヘッドが波打つような軌道になりやすく、クラブヘッドの軌道やフェース向きのコントロールが難しくなるが、インパクトでヘッドを加速させ飛距離を出すという点ではプラスに働く側面がある。
■シャフトクロスの度合いを抑える
米ツアーを目指すにあたり飛距離はマストだが、それだけでは戦えない。だからリーのスイング要素を取り入れようとしたのではないだろうか。
リーのスイングは、ドライバーショットの時でも、シャフトが地面と平行ラインまでいかず、コンパクトなトップオブスイングの形になっている。
さらに、シャフトが飛球線と平行ラインよりも左を向くレイドオフだ。
このトップオブスイング、そしてそこからの切り返しのイメージが、今の蟬川にはまったのではないだろうか。
スイング作りは、やりたい動きをそのままイメージしてもその動きにはならない。極端にイメージしてそれを反復することで、やっと少し目指す動きに近いものになる、というのがスイング作りである。
リーのスイングはある意味、蟬川のスイングとは真逆。だから、そのイメージを持つことで、蟬川のスイングの強まり過ぎていた部分が適度にそぎ落とされたのかもしれない。
■対極にある動きや形のイメージを持つ
多くの一般ゴルファーも、自身のスイングに何らかの課題を抱えているだろう。そして「課題を克服してこうなりたい」という、理想があるはずである。
課題を克服するためには理想をそのままイメージするのではなく、現状と対極にある動きや形をイメージしたい。
例えば、バックスイングで腰が右にスウェーしてしまう癖を直し、構えたその場で腰を回す動きを理想とするのであれば、構えたその場で腰を回そうとしても求める結果は得にくい。
腰を左にずらしながら(左軸イメージで)腰を回すイメージを持つことで、元の癖と調和され、構えたその場で腰を回しやすくなる。
テークバックで開いてしまうフェースをスクエアにしようとするのであれば、スクエアをイメージしてもそうはならない。フェースを閉じる、それも極端に閉じるイメージを持つことで、フェースがスクエアに近づく。
感覚と実際は異なる。それを大前提とすることで、理想のスイングに近づきやすくなる。
◆圧倒的なアイアン精度 スコッティ・シェフラーの変則的なスイングに見るボールに力が伝わる動きとは
◆河本結の復活を支えたパッティングに学ぶ、距離感を安定させパット数を減らすポイント
◆【最新】松山英樹や久常涼は今いったい何位……男子ゴルフ世界ランキング
著者プロフィール
野洲明●ゴルフ活動家
各種スポーツメディアに寄稿、ゴルフ情報サイトも運営する。より深くプロゴルフを楽しむためのデータを活用した記事、多くのゴルファーを見てきた経験や科学的根拠をもとにした論理的なハウツー系記事などを中心に執筆。ゴルフリテラシーを高める情報を発信している。ラジオドラマ脚本執筆歴もあり。