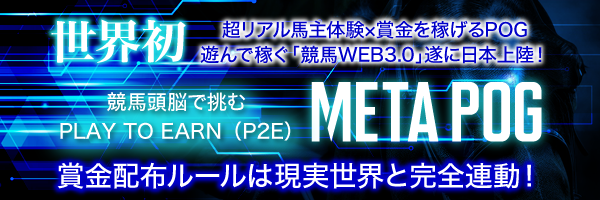齊藤さんの言葉通りスポーツ・ビジネス界において、P&Gの戦略などは日本企業にとっても手本となるのではないだろうか。
松井秀喜さんの同僚としても知られるニューヨーク・ヤンキース元主将デレク・ジーターが立ち上げた「プレイヤーズ・トリビューン」というデジタルメディアがある。アスリートが自身の意見をそのまま発信できるサイトとして一線を隠す存在だが、その「母の日」企画をP&Gがサポートした。世界のTOPアスリートが「Dear Mom」と題し、母への感謝と思いを綴る……この企画のスポンサーがP&Gだ。しかし記事中にも、周辺にも一切、P&Gの広告も商品も表示されない。「Dear Mom」という記事のひとつひとつにsupported by P&Gと表記されるだけ。
P&Gがいかに母の日を、または真摯に母という存在をサポートしているか…その哲学を感じ取らざるをえない。
Advertisement
齊藤恵理称(さいとう・えりな)
●フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社スポーツ&エンターテインメント・ジェネラルマネージャー/シニア・バイス・プレジデント
筑波大学大学院体育学修士取得後、アップルコンピュータでマーケティングコミュニケーション、“Think different.”グローバルブランドキャンペーンを担当、その後プラダのブランドマネージャーなどを経て2009年、フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社に入社。国内外企業のスポーツスポンサーシップ、戦略コミュニケーションを提供。
2021年春、早稲田大学大学院 スポーツ科学博士終了。一般社団法人日本ゴルフツアー機構広報アドバイザー、一般社団法人ホッケージャパンリーグ理事も兼務する。
◆【インタビュー前編】スティーブ・ジョブズに学んだコミュニケーション哲学
■スポーツをビジネスの課題解決としてどう使うか……
日本ではこうした企業哲学を感じさせるようなコミュニケーション戦略を見る機会は少ない。どうしても、目の前にある商品を連呼し、商品を売り裁くための短絡的で利己的なCMに偏りがちである。
「トヨタさんのようなグローバル企業を例にとれば理解してもらえるとおり、コミュニケーションには『社員啓蒙』も含まれています。五輪を活用し、スポーツの力を活かし、社会貢献の実現を目指します」、齊藤さんは、そのためのスポンサー活動、コミュニケーション戦略だと力説する。
上記の証左のようにトヨタは今回の東京五輪についてCM出稿をせず、また豊田章男社長も現地出席を見送るというニュースが流れた。五輪に向け、次々と問題点が浮上する今大会、トヨタの哲学やトップスポンサーとしての役割を踏まえた判断がなされたのだろう。
「スポーツは単純にプロダクトやブランドを売るために、広告をどこに露出するか……という発想ではなく、スポーツを企業の課題解決や事業成長にどう活かすかです」、こうして目的な明確でないと、コミュニケーションの設計は難しいのだという。
「日本では時折、スポンサーシップそのものがトップダウンで決まってしまう。せっかく投資するのであれば、そのメリットをあぶり出さないといけません。日本の企業は、コミュニケーションの目的設計から必要です。事業設計があり、将来的戦略があり、その上でスポンサーをすべきです」。こうした言葉は、極めて常識的な戦略に聞こえる。
「Appleにはすでにブランド力がありますが、それでもコミュニケーションには手を抜きません。『なぜAppleを作ったのか』と同様に、『なぜこのプロダクトを作ったのか』、「なぜ」というストーリー、その背景に共感を呼ぶことで、Appleは見事に復活を成し遂げました」。日本の企業コミュニケーションは「What」と「How」しかない。「Why」が必要なのだと釘を刺す。
日本企業にとっては、少し耳が痛い話題だろう。しかし今後の戦略構築に際しては、参考にすべき提言のはずだ。齊藤さんが提言するコミュニケーション戦略の必須3条件は以下の通りだ。
・明確な目的設計
・対象の明確化
・将来戦略の明示
現在、新型コロナ禍にあるため今後、企業が社会にどう直結するのか、社会にどう貢献するか、社の役割を明確にする必要があるという。自社だけではなく、社会全体への影響を考慮すべきであり、「これが世界の時価総額TOP50企業に、現在はほとんど日本企業がランクしない理由ではないか」と斎藤さんは考えている。